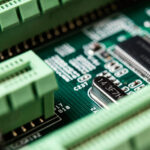医療機関におけるセキュリティは、もはや情報システム担当者だけの課題ではありません。電子カルテや検査機器などのIT化が進み、患者の個人情報から診療データまで膨大な情報が日々やり取りされています。
その一方で、サイバー攻撃や内部不正、さらには施設への侵入など、脅威は年々多様化しています。ひとたび漏えいやシステム停止が起これば、業務への影響はもちろん、患者の命や信頼を揺るがす重大な問題につながります。
本記事では、医療機関が直面するセキュリティリスクの全体像を整理し、必要な対策の視点と実践のポイントを分かりやすく解説します。日常業務を守り、安心できる医療体制を支えるための参考にしてください。
医療機関におけるセキュリティとは
医療機関のセキュリティは、サイバー攻撃対策だけでなく、施設の防犯や内部不正防止まで幅広い領域を含みます。患者の個人情報や診療データを守り、医療の継続性を確保するためには、情報・システム・物理環境すべてを対象とした多角的な対策が欠かせません。
医療機関が狙われやすい理由と特徴
医療機関が攻撃者にとって格好の標的となるのは、まず取り扱う情報の価値が極めて高いからです。患者の個人情報や診療記録は、犯罪組織にとって転売や不正利用の対象となりやすく、金融情報以上に需要があるとされます。さらに、病院やクリニックでは電子カルテ、検査機器、院内ネットワークなど多様なシステムが連携しており、一部が侵入されるだけで全体が機能不全に陥るリスクがあります。
また、医療機関は「止められない現場」であるため、業務継続が何より優先されます。そのため、システムがランサムウェアに感染しても支払いに応じざるを得ない状況に追い込まれるケースがあるのです。加えて、医療従事者はセキュリティ教育を専門に受けていない場合が多く、パスワード管理やメールの開封などでヒューマンエラーが起きやすい点も狙われやすさにつながります。こうした背景から、医療機関は他業種と比べても攻撃の標的になりやすいという特徴を持ちます。
医療情報・システム・施設すべてを守る必要性
医療機関のセキュリティは、単に情報漏えいを防ぐだけでは不十分です。電子カルテや医療機器を扱うITシステムはもちろん、院内の物理的なセキュリティも同等に重要です。たとえば、サーバールームやナースステーションへの不正侵入を許せば、情報だけでなく機器自体の盗難や操作ミスによる事故につながる恐れがあります。
さらに、診療データや検査結果が改ざん・消失すれば、医療の正確性や安全性に直結し、患者の生命を危険にさらしかねません。また、システム停止が続けば手術や検査が延期され、地域医療全体に深刻な影響を与えることもあります。こうしたリスクを考えると、守るべき対象は情報だけでなく、システム全体から施設、人材管理まで広がります。セキュリティを総合的に捉え、デジタルとフィジカル両面での対策を講じることが、医療機関にとって欠かせない姿勢と言えるでしょう。
主なリスクの種類
医療機関を取り巻くリスクはサイバー領域に限らず多岐にわたります。マルウェア感染や情報漏えい、内部不正に加え、IoT医療機器や物理的な侵入リスクも存在します。それぞれのリスクを理解し、適切な対策を講じることが安全な医療提供の前提となります。
サイバー攻撃・マルウェア・ランサムウェア
医療機関を狙ったサイバー攻撃は年々増加しており、特にランサムウェアは重大な脅威です。ランサムウェアはシステムや電子カルテを暗号化し、解除の代わりに身代金を要求する攻撃で、医療現場の継続性を直撃します。病院は業務停止が許されないため、支払いに応じてしまう事例も報告されています。
また、一般的なマルウェア感染やフィッシング攻撃も多く、医療従事者の不注意によるメール開封や添付ファイルの実行が感染経路となるケースが少なくありません。
さらに、攻撃者は医療情報システムの脆弱性や古いOSの機器を狙う傾向があり、定期的な更新が滞る現場は特に危険です。こうした攻撃が成功すると、患者データの流出、診療停止、さらには命に関わるリスクに直結します。医療機関はサイバーリスクを「必ず狙われる前提」で捉えることが不可欠です。
漏えい・不正アクセス・内部不正
情報漏えいの原因は外部攻撃だけではなく、内部の人間による不正や不注意も大きな割合を占めます。たとえばUSBメモリや私用端末への不正コピー、意図的な情報持ち出し、あるいは廃棄処理の不備による紙媒体からの流出などが挙げられます。
また、アクセス権限の管理が不十分な場合、必要のないスタッフが患者データを閲覧できる状態になり、内部不正や誤閲覧のリスクを高めます。さらに、医療現場は人の出入りが多いため、端末の無施錠やIDカードの貸し借りといった小さなルール違反が重大な漏えいにつながるケースもあります。内部不正は外部攻撃と異なり検知が難しく、発覚が遅れやすい点も特徴です。
医療機関では技術的な制御だけでなく、アクセス権の厳格化、監査ログの確認、職員教育を通じたルール定着が欠かせません。
医療機器・IoT機器リスク
近年の医療現場では、CTやMRI、人工呼吸器といった医療機器がネットワークに接続され、IoT化が進んでいます。これらは診療の効率化や遠隔モニタリングを可能にする一方で、セキュリティ上の新たなリスクを生み出しています。
多くの医療機器は導入後のライフサイクルが長く、最新のセキュリティパッチが適用できない場合も多いのが実情です。その結果、脆弱性を突かれたサイバー攻撃によって機器が停止し、診療が中断する危険性があります。また、IoT機器は一度侵入されると院内ネットワーク全体への踏み台として利用されるリスクもあり、被害が拡大する可能性を秘めています。
患者のバイタルデータや検査結果が不正に取得・改ざんされれば、医療の安全性や正確性に直結する大きな問題となります。医療機関は、IoT機器を含むセキュリティリスクを想定し、専用ネットワークの分離やアクセス制御を徹底することが不可欠です。
物理的リスク・施設侵入・盗難
サイバーセキュリティが注目されがちですが、物理的なリスクも医療機関においては無視できません。病院やクリニックは不特定多数の人が出入りする場所であり、来訪者を装った不審者がサーバールームやナースステーションに侵入する可能性があります。もし電子カルテ端末やバックアップ媒体が盗難に遭えば、甚大な情報漏えいにつながります。
さらに、薬品庫や放射線機器の不正利用など、医療特有のリスクも存在します。これらは患者の安全を直接脅かすだけでなく、施設全体の信頼失墜にも結びつきます。
医療機関に必要なセキュリティ対策の視点
医療機関におけるセキュリティ対策は、多面的な視点から計画する必要があります。法令やガイドラインの順守を前提としつつ、システム面・運用面・人材教育まで含めて組織全体で取り組むことが重要です。ここでは、特に優先度の高い視点を整理します。
ガイドライン・法規制に関する対応を遵守する
医療機関のセキュリティ対策を考えるうえで外せないのが、法規制や業界ガイドラインへの対応です。厚生労働省が公表している「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」では、個人情報保護やシステム運用における基本的な要件が定められています。これらは単なる指針ではなく、診療報酬算定や監査の場面でも参照されるため、実務上の遵守が不可欠です。
主な対応項目には、アクセス権限の適正管理、システム監査ログの取得・保存、個人情報の暗号化、外部委託時の契約管理などがあります。また、個人情報保護法やマイナンバー関連の規制も医療現場に影響を及ぼしており、違反すれば法的責任や社会的信用の失墜につながります。
さらに、国際的な標準であるISO27001やISMS認証を取得することで、患者や取引先に対して高い信頼性を示すことも可能です。法規制対応は「守り」だけでなく、病院の信頼ブランドを支える「攻め」の姿勢としても重要な役割を果たします。
ネットワーク分離と多層防御の仕組みを取り入れる
医療機関では、一度サイバー攻撃を受けると被害が拡大しやすい構造を持っています。こうした状況を防ぐために有効なのが「ネットワーク分離」と「多層防御」の考え方です。
ネットワーク分離では、診療システムとインターネット接続系を明確に切り分け、感染が広がらない構造を作ります。たとえば、検査機器や電子カルテ端末は院内専用ネットワークに限定し、一般の閲覧用PCとは接続を分けることで、マルウェアの拡散リスクを低減できます。さらに、アクセス制御を強化し、利用者ごとに閲覧・操作できる範囲を最小限に絞ることも有効です。
また、多層防御では、ファイアウォールやIDS/IPS、EDRといった複数の仕組みを組み合わせ、侵入を前提にした対策を重ねていきます。単一の仕組みに頼るのではなく、複数のバリアでリスクを分散させることで、万一の突破時にも被害を最小化できます。医療機関にとって、これらの技術的な備えは「止めない医療」を守るための必須条件といえるでしょう。
エンドポイント保護・EDR/XDRなどを導入する
電子カルテ用のPCや医療スタッフが使用する端末は、日々の診療で頻繁に利用されるため、攻撃者にとって侵入口となりやすい領域です。従来型のアンチウイルスソフトだけでは、未知のマルウェアや標的型攻撃を十分に防げないケースが増えています。そこで注目されているのがEDR(Endpoint Detection and Response)やXDR(Extended Detection and Response)の導入です。
EDRは端末の挙動を常時監視し、不審な動きを早期に検知して対応につなげる仕組みです。XDRはさらに範囲を広げ、サーバーやクラウド、ネットワークまでを横断的に監視するため、組織全体での脅威検知が可能になります。医療現場では一つの端末感染が全体の診療業務に波及する恐れがあるため、これらの仕組みを導入することで被害の早期封じ込めが実現します。重要なのは、導入後もアラート運用を定着させ、現場のIT担当やセキュリティベンダーと連携して対応体制を確立することです。
定期的な脆弱性診断・パッチ運用を行う
古いOSを搭載した医療機器や、更新が滞っているシステムは、攻撃者にとって絶好の標的となります。特に医療機器は導入から長期間利用されることが多く、メーカーのサポート終了後も現場で稼働し続けるケースが珍しくありません。こうした状況を放置すると、既知の脆弱性を突かれ、感染や不正アクセスが発生する可能性が高まります。
有効な対策としては、まず定期的な脆弱性診断を実施し、システムや機器に潜むリスクを可視化することが重要です。その上で、提供されているセキュリティパッチを計画的に適用し、更新を怠らない仕組みを整える必要があります。
ただし、医療現場はシステム停止が業務に直結するため、メンテナンス計画を診療スケジュールと調整する工夫も求められます。また、更新が不可能な機器についてはネットワーク分離やアクセス制限でリスクを補うことが現実的です。定期診断とパッチ管理を組み合わせることで、攻撃の入口を閉じ、医療機関全体のセキュリティ水準を安定的に高めることができます。
バックアップ設計・事業継続計画(BCP)対応をつくる
電子カルテや検査データは診療の根幹を担う情報であり、消失すれば患者の生命や治療に深刻な影響を及ぼします。そのため、定期的なバックアップ設計と事業継続計画(BCP)の策定は必須です。
バックアップは、フルバックアップに加えて差分・増分バックアップを組み合わせることで効率化を図り、万一の際に迅速な復旧が可能となります。保存先はオンプレミスだけでなく、クラウドやオフサイトの外部施設を併用することで災害リスクも分散できます。また、バックアップを「取得して終わり」にせず、定期的に復旧テストを行うことが、実際の緊急時に確実に機能するかを確認するうえで重要です。
BCPの観点では、診療を継続するために最低限必要な機能を明確化し、代替システムやマニュアル運用に切り替える手順を事前に定義しておく必要があります。バックアップとBCPを両輪で整備することで、想定外の事態にも揺るがない医療体制を確保できます。
認証・権限管理・ID管理を徹底する
医療現場は多くのスタッフが端末やシステムにアクセスするため、認証や権限管理が甘ければ情報漏えいや不正利用のリスクが高まります。患者データや診療記録は機微情報であるため、アクセス権限を「必要最小限」に絞ることが原則です。
具体的には、システムごとに利用者ごとの役割(医師・看護師・事務職員など)を定義し、必要な範囲だけにアクセスできるように設定します。さらに、IDやパスワードの共有は禁止し、個人単位のログを残すことで責任の所在を明確にすることが大切です。加えて、多要素認証(MFA)の導入によって、外部からの不正アクセスを防ぐ効果が高まります。
また、異動や退職に伴うアカウント削除の遅れは大きなセキュリティリスクとなるため、ID管理のライフサイクルを統制する仕組みも不可欠です。定期的にアクセス権限を見直し、不要な権限を削除する運用ルールを徹底することで、内部不正や情報漏えいを未然に防ぐことができます。認証・権限管理は、医療情報を安全に扱う基盤として最も基本的かつ重要な対策の一つです。
教育や啓発の定着化
医療機関におけるセキュリティ対策は、システムや設備の導入だけでは完結しません。最終的に運用するのは人であり、従業員一人ひとりの意識や行動がセキュリティの成否を左右します。そのため、教育と啓発活動を継続的に実施し、日常業務に定着させることが重要です。
具体的には、メールを装ったフィッシング攻撃やパスワード管理の重要性といった基礎的な内容を、定期的な研修やeラーニングを通じて学習させる方法があります。また、シミュレーション演習を行い、実際の不審メール対応やインシデント発生時の行動を体験させることで、実務に直結するスキルを養えます。さらに、啓発ポスターや院内掲示、簡単なチェックリストを活用することで、日常的に意識を呼び起こす工夫も有効です。
大切なのは一度の研修で終わらせるのではなく、定期的な振り返りや評価を組み込み、改善サイクルを回し続けることです。教育を単なる形式的なものにせず、医療現場に根づいた文化として定着させることで、全体のセキュリティレベルを安定的に高めることができます。
インシデント対応体制を整える
どれほど堅牢な対策を整えても、セキュリティインシデントを完全に防ぐことはできません。そのため、発生を前提とした「対応体制」を整えることが不可欠です。医療機関では、情報システム部門や外部の専門ベンダーと連携した緊急対応フローをあらかじめ策定し、役割分担を明確にする必要があります。
インシデント対応では、まず検知のスピードが鍵となります。そのため、システムや端末のログを収集・監視し、不審な挙動を早期に発見できる体制が求められます。SIEM(セキュリティ情報イベント管理)やSOC(セキュリティ運用センター)を活用すれば、複数システムにまたがる異常を相関的に把握することが可能です。また、対応訓練を定期的に行い、システム停止や情報漏えいを想定したシナリオをシミュレーションしておくことで、実際のインシデント時にも混乱を最小限に抑えられます。
さらに、対応後の振り返りと改善も欠かせません。原因分析を行い、再発防止策をシステムや運用ルールに反映させることで、組織全体の耐性を強化できます。インシデント対応とログ監視を一体で整備することが、止めない医療を守る最後の砦となります。
小規模な医療機関向け!実践のポイントは?
大規模病院と異なり、小規模なクリニックや診療所では専任の情報システム担当者がいないケースも多く、限られた予算と人員の中でセキュリティを確保する必要があります。重要なのは「すべてを一度に導入する」のではなく、リスクの大きい部分から優先順位をつけ、段階的に対策を進めることです。
まず取り組むべきは、患者データを扱う端末や電子カルテの基本的な保護です。強固なパスワードポリシーを設定し、多要素認証を導入するだけでも外部からの不正アクセスの多くを防げます。さらに、OSやアプリケーションを常に最新状態に更新し、アンチウイルスやEDRといったエンドポイント保護を導入することで、感染リスクを大幅に下げられます。
次に考えたいのがバックアップ体制です。定期的にデータを外部メディアやクラウドに保存し、復旧テストを行っておくことで、万一の障害やランサムウェア感染時にも診療を継続できます。シンプルな仕組みであっても「確実に復元できる」ことが重要です。
また、小規模機関では人員の入れ替わりや役割兼務が多いため、アクセス権限の見直しを定期的に行うことが欠かせません。全員が「誰がどこまでアクセスできるか」を理解している状態を作ることで、内部不正や誤操作のリスクを最小化できます。
加えて、職員教育を年1回でも実施し、不審メールや端末管理の注意点を共有するだけでも現場の意識は大きく変わります。大規模な仕組みが整っていなくても、日常的な習慣づけによってセキュリティ文化を根づかせることが可能です。
小規模だからこそ、限られた投資を的確に行い、簡易かつ実効性の高い対策を継続していくことが、持続可能な医療セキュリティにつながります。
まとめ
医療機関におけるセキュリティは、患者の個人情報を守るだけでなく、診療の継続性と信頼を確保するための基盤です。サイバー攻撃や内部不正、医療機器の脆弱性、物理的リスクまで幅広い脅威が存在する中で、法規制遵守や多層防御、バックアップ体制の整備といった多角的な対策が欠かせません。小規模な診療所でも、段階的な導入と職員教育を組み合わせれば、現実的かつ持続可能な対策を実現できます
。セキュリティは一度整備して終わりではなく、定期的な見直しと改善を繰り返すことで強固なものになります。安心して医療を提供できる環境を維持するために、自院に適したセキュリティ対策を今一度見直してみましょう。